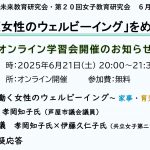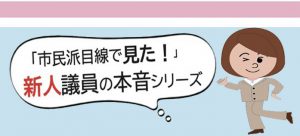
職業生活の充実等に関する法律
風船を針で突いたような心情だった
加害者目線のお話をすると、他市ではこんな事例もありました。報道で、明石市の泉市長が議員に暴言をはいた事に対して、パワハラだと騒がれていたのですが、その記事の中でこんな言葉を目にしました。「まるで風船を針で突いたかのようだった」と。
一方的に文句を言っただけのハラスメントだったのでしょうか。なぜなら、この時の状況でいうと泉市長は議員らから先に問責決議を出され精神的苦痛を与えられた立場にいました。これまでも、議案に対する議員からの反発や、専決処分を行わないといけない理由もあったようです。
市長と議員といえば、上司と部下とは違い越権行為が働く関係でもないし、言わば対等な立場のはずです。しかし、状況によっては議員は市長よりも市政を動かせる力をつけることができる存在になりうるのではないでしょうか。なぜなら、議員は数を使い意図的に賛否を操り政策の邪魔をすることもできる立場にいます。市長にとって議員とは、議案という人質をとられた歯向かえない存在になりうると感じています。
表でわかりやすい暴言をはいてしまいパワハラとなってしまわれた泉市長に対して、目立たない裏では議員がコソコソと精神的苦痛を与え続けていたとしたら、これも立派なパワハラだと思います。だから、その風船がとうとう破裂してしまったという表現が当てはまったのかもしれません。
何もなかった所からのいきなりの行動ではなくて、長年に渡り集団から嫌がらせ行為を受けていた事への意趣返しとなってしまったのではないでしょうか。どうしてそんな態度になったのかと言う原因があったということです。ちなみに議員が提案した問責決議の審議が行われた中継を見ていましたが、法を犯している訳でもなく、まるでとってつけたような理由を並べているように個人的には感じました。
本当に強い人は、自分が成し遂げたい事への思いに勝るものはないので、多少の横槍がきてもめげないはずです。ただ、どれだけ温厚で誠実な人でも、時に気持ちや態度が急変することがあり、何か追い込まれるようなきっかけや原因があると言うことはないでしょうか。
一生懸命やっている人にしてみれば、邪魔ばかりされ続けると、誰だって怒りたくもなるかもしれません。追い込まれるものがあって、それに対して自分の意思が強い人ほど、我慢の限界という状態になって、凧の糸がプツンと切れたようにやる気を無くしてしまう心境は理解するところです。







![【YouTubeモコモコ通信 】問責決議で暴走したメディアとSNSの真相[vol.3]](https://takaoka-tomoko.me/wp-content/uploads/2025/06/スクリーンショット-2025-06-24-14.00.34-e1750741360204-150x150.png)
![【YouTubeモコモコ通信 】問責決議で暴走したメディアとSNSの真相[vol.2]](https://takaoka-tomoko.me/wp-content/uploads/2025/06/mqdefault-150x150.jpg)
![【YouTubeモコモコ通信 】問責決議で暴走したメディアとSNSの真相[vol.1]](https://takaoka-tomoko.me/wp-content/uploads/2025/06/maxresdefault-150x150.jpg)