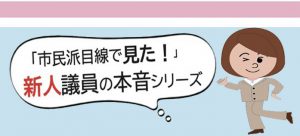
黙認している意味がわからない
議員になって、はじめて「申入書」というものを作成しました。代表者会議での協議事項を申し立てたものです。そして、令和3年9月13日に「議会におけるハラスメントの防止に関する申し入れ」を議長に提出しました。
芦屋市議会では、議員にむけての「芦屋市議会ハラスメント等防止に関する指針」(以下、「指針」)を策定するために、代表者が集まり協議中です。そこで私は、ある事例について重要なことがあるのに、一度も検証されていないことについて、議員間での協議の機会を設けてもらうために動くことにしました。
議員が市職員の事案を取り扱う時は、プライバシーの侵害にならないように個人情報の取り扱いには、慎重になります。議員は、そのことをしっかりと理解し気をつけなければいけないからです。議会全体としての取り組みの中を振り返り、議員としてこれまでの言動に問題があったのならば、本人が自覚を持っておかなければ、ハラスメント指針を作ったとしても再発防止としての本来の効果が見込めないと思っています。
申し入れた目的は、そこに出てくることに該当する議員の言動が、ハラスメント問題を扱う上で、議員としての倫理に問題があったと感じているからです。指針を作る前に、そのことを議会として調査しておかなければいけないと考えていました。
どうしても真相を認めようとしない
市職員がハラスメント行為を行った場合、それが認定がされると市長や副市長には、監督責任がかせられてきます。それが行われたのが、3名の議員がトップの責任を問い、伊藤市長に対し問責決議を突きつけたことでした。市長にそこまで責任を追及してきた議会ですが、ハラスメント事案を不誠実に公で取り扱った議員のモラルについては検証していません。指針をつくるというならば、そこはきちんと公平に議会としても確認しておかなければいけないと私は思ったのです。
そこで、9月13日に議長室に向かい、「申入書」を提出する運びとなりました。同会派の中村議員と一緒に、副議長と事務局長の立ち会いのものと、議長にその申し入れの主旨をお伝えしました。ところが、議長からは「申入書の中に出てくる内容は、指針には関係ない。」という回答がありました。協議が必要であるという私の思いを汲み取っていただけていないように感じました。
たしかに、この事例は行政側とのことです。「当事者ではない議員の事例は扱わない」という見解をされているのかもしれません。議員が直接のハラスメント被害者や加害者だったわけではないので「議員におけるハラスメント指針」とはならないという判断をされていました。しかし、今回私が申し入れた内容は、そういう直接的な意味合いのことではなかったのです。
市職員に問題が浮上すると、処分に対し議員は報告を受け、発言できる立場にいます。なので、聞く立場の議員も、市長に問責決議を追わせたのと同様に、個人情報を伴う事案を取り扱う上で、最善の注意と理解が必要な立場にいました。
議員のモラル違いひとつで結論もかわり、大変な自体も起こしかねないのです。だからこそ、デリケートな事案を取り扱う上で議員は、相手の気持ちに寄り添い慎重にならなければいけないという自覚を持ち、配慮することが大切だと考えています。私が今回、申入書の事例にあげた議員の言動は、職員への配慮にかけていたことは明らかです。
行政を監視する立場にいるのが議員です。その議員だからこそしっかりと問題意識を持ち、話を聞く立場として知識を高めて行く必要があると考えています。だから、議会としても指針が必要だということになったから、策定しているわけでした。
そして、議会全体としてしっかり理解し共有することで、今後の運営に指針を役立ててほしいと願っています。誤った議員の言動ひとつによって、職員の人生にも左右し大きく影響を及ぼします。間違った判断が起こらないように、防止をしてこそ、はじめて「議員としての指針」が生かされるのではないでしょうか。
ただ「指針」を議会はつくりました、ということが大事なのではなくて、理解しているフリでは意味がなく、議会として是正し、一定のけじめをつけれてこそ、今後の姿勢を市民に示せたことになると私は思います。















